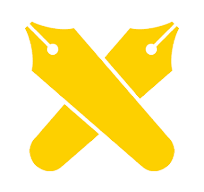人文科学 浜田 和範
世界の文学を読む

MESSAGE
この研究会では、いわゆる「欧米」と認識される地域を取り巻く場所から/について書かれた文学作品を読んでいきます。
ことばを介して、日常生活で思いを馳せる機会の少ない土地に旅立つこともあるでしょうし、よく知っているはずだった地域の知られざる部分に踏み込むこともあるかもしれません。その過程の中、遠く離れた地で繰り広げられる思考や感情や行動に思わぬ近しさを感じることもあるでしょうし、逆に、きわめて身近なはずの存在が「他者」としての絶対的な隔たりを露わにしたりするかもしれません。そのような出会いは、あなたの知覚や思考の幅を、ほんの少しではあっても決定的に拡げることになるでしょう。
世界というものの広さに戸惑いながらも、彼ら/彼女らが発する声を受け止め、論文として自分なりに応答してみることで、あなた自身が更新される。当研究会が、そんな場になればと思います。
春学期は、教員の選んだ作品を講読することで、さまざまな地域の言語芸術に関する基礎知識を蓄えつつ読解の技能を身につけます。並行して、自分が言葉を尽くしてみたいと思える対象(作品、作家、テーマetc.)を見定めていきます。
秋学期は、個々の履修者が選んだ研究対象の作品を読みつつ、関連文献を探して報告を重ねることで研究対象として文芸作品に向き合い、副専攻論文の構想を固めていきます。特に4年生のメンバーは、副専攻論文の執筆に向かってもらいます。報告と討議を経て、思い思いの探究を形にしていきましょう。
PROFESSOR & MEMBER
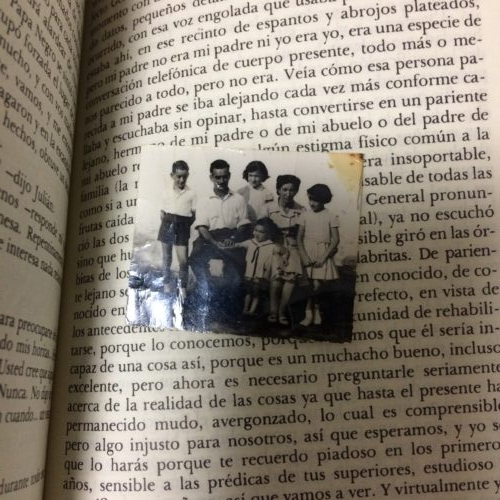
ウルグアイとアルゼンチンを中心に、20世紀以降のラテンアメリカ文学を研究しています。並行して、作品の翻訳紹介も手がけています。
春学期の授業では「遭遇」や「独裁を読む」といったキーワードのもと、南アフリカやアルゼンチン、コロンビア、ベラルーシといった地域の小説作品を読んできました。今後は、アジアやオセアニアといった地域の作品も取り上げてみたいと考えています。
担当教員の専門分野を意識して、というわけでもないと思いますが、履修者が「授業で読みたい!」と挙げてくる作品は、当初はラテンアメリカのものが多めでした。最近は東欧やインドなど選んでくる土地が実にバラけてきて、こちらも触発されつつ楽しんでいます。好きな作家が褒めていたあの短篇集、最近ニュースで話題になったあの長篇小説、旅行したことがあって気になる国、といった具合に、それぞれが自分のアンテナに引っかかったものを講読の形で共有し、報告と討議を重ねてことばを研ぎ澄まし、読み応えのある知的成果物を仕上げています。
LINKS
入ゼミ案内
あなたが立とうとする地平はあまりに広く、ともすれば途方に暮れてしまいます。受講にあたり、とりたてて課題は設けません。
とはいえその景色の中で迷わず足跡を残すには、論文の形で言葉にしてみたい対象(テーマ、作家、地域、個々の作品など)を可能な限り定めていくことが必要です。初回授業で、興味のある地域やテーマ、作家や作品について、その場で説明できるよう用意してもらえればと思います。
News お知らせ
No posts were found.