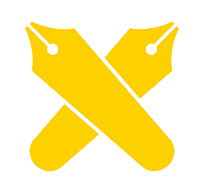MESSAGE
2026年度に新規開講のゼミです。
慶應に来てから約15年になりました。慶應の学生は、キラキラ輝いていて、勉強にも遊びにも全力で打ち込める器用な人が多いと感じます。私自身は、とても不器用な人間なので、地味に地道に学び、ゼミ生同士ゆっくり友情を育む大学での居場所となるゼミを目指したいと思います。
担当教員の専門は民法ですが、ゼミでは、民法と高齢者法を扱います。高齢者・高齢社会に関する法的問題を横断的に扱う高齢者法は、アメリカのロースクールでは常設科目として一般的ですが、日本ではまだ未確立の法分野です。その内容は多岐にわたり、例えば、高齢消費者被害、高齢者の加害・被害(民事、刑事)、高齢者の就労、年齢差別、高齢者と金融取引、高齢者の婚姻・再婚、老親扶養・介護、高齢者の住まい(建物賃貸借、有料老人ホーム等の施設入居契約、施設の倒産、リバースモーゲージ、リースバック、配偶者居住権等)、高齢者の財産管理・承継(遺言・相続、贈与、生命保険、信託、その他民法外の財産移転制度等)、高齢者と医療(終末期医療、医療同意・代理決定)、無縁高齢者、孤立・孤独死、葬儀・埋葬、墓地、死後事務委任、意思能力・行為能力、成年後見制度、高齢者福祉(生活保護・年金、介護保険、医療給付等)、高齢社会のインフラ(バリアフリー、地域社会における生活基盤の安全・安心)、高齢者虐待などが含まれます。
世界一の超高齢社会である日本では、行政、政治のみならず、ビジネスでも、高齢者に関わる法的問題を避けて通ることはできません。公務員志望者、民間企業就職予定者から研究職希望者まで、多様な問題意識と関心を持った人の参加を期待します。
PROFESSOR & MEMBER

1999年、東京大学法学部卒。
上智大学専任講師・准教授を経て、2012年、慶應義塾大学准教授。
現在、法科大学院教授。博士(法学)東京大学。
LINKS
入ゼミ案内
【曜日・時限】 金曜日3限
【兼ゼミ】 可
【4年生】 可
【他学部生】 可
【卒論】 任意
【必修授業、成績要件】 特になし
★入ゼミを希望される方、質問がある方などは、メール(k-nishiあっとまーくls.keio.ac.jp)でご連絡ください。
News お知らせ
No posts were found.