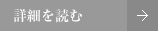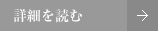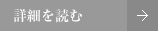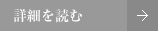
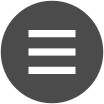
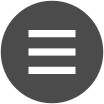
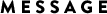
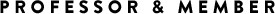

森 聡
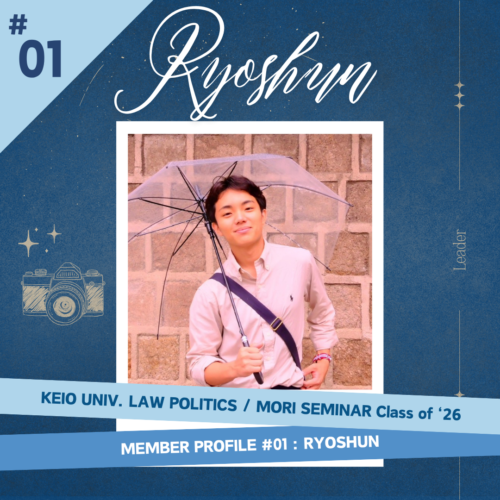
長谷川良俊
3年
ゼミ長
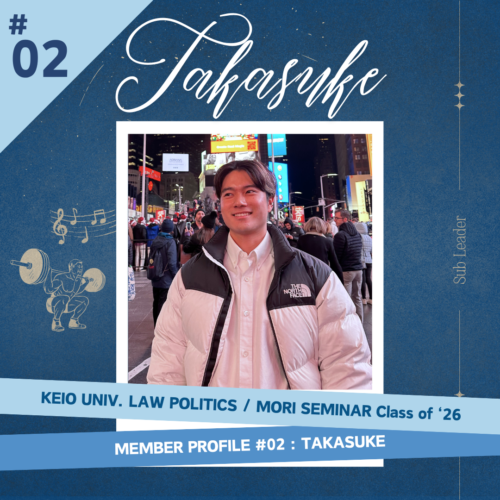
菅井嵩介
3年
副ゼミ長
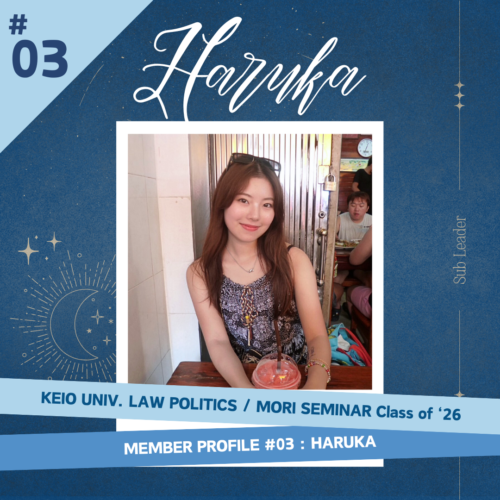
川野晴香
3年
副ゼミ長
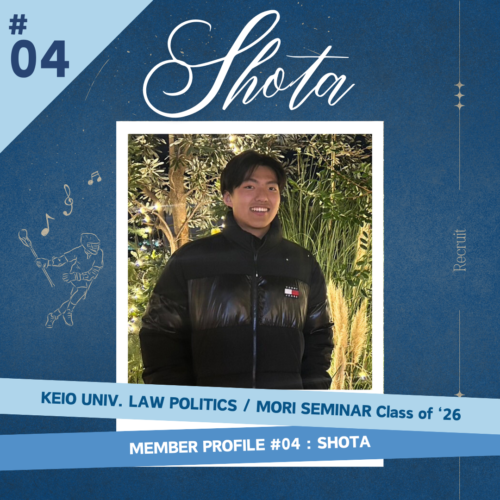
花岡奨泰
3年
リクルート係

杉森美音
3年
リクルート係
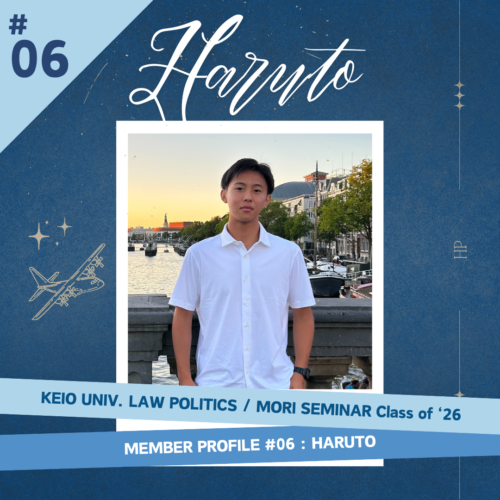
寺岡晴人
3年
HP係

竹内菜月
3年
合同ゼミ係
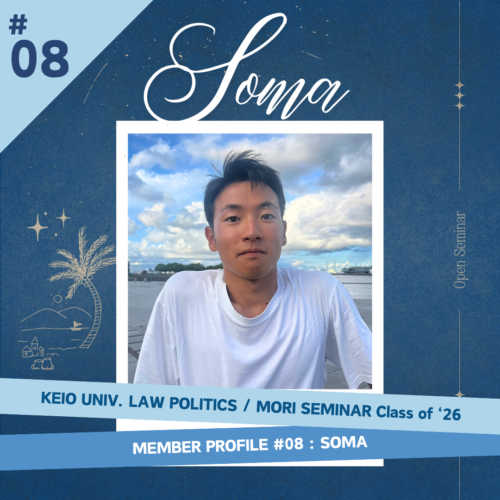
下田颯真
3年
オープンゼミ係
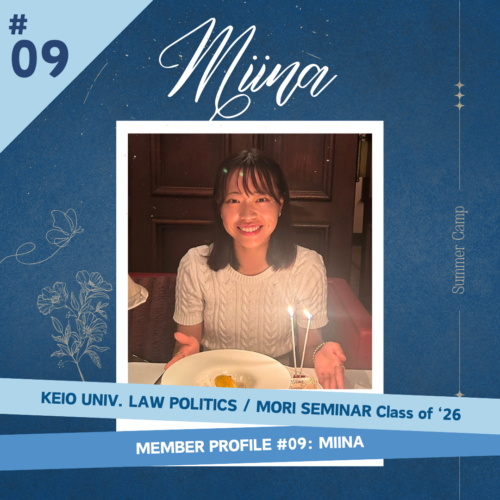
鈴木美維奈
3年
合宿係
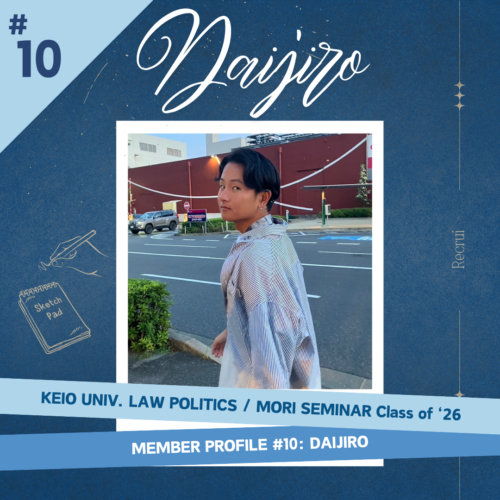
久保田大二郎
3年
リクルート係

三宅希和
3年
リクルート係
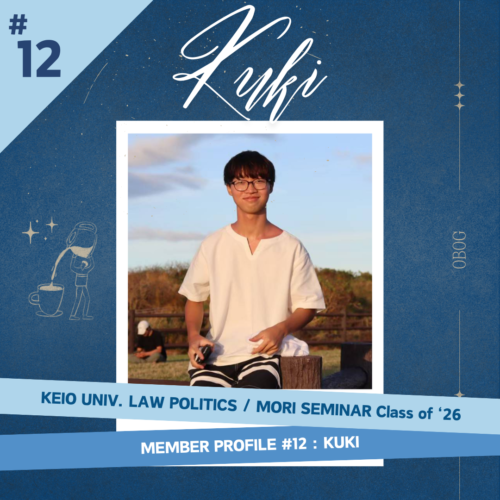
吉澤空輝
3年
OB・OG会係

小野寺葵
3年
HP係

山口創希
3年
OB・OG会係

三宅咲文
3年
リクルート係
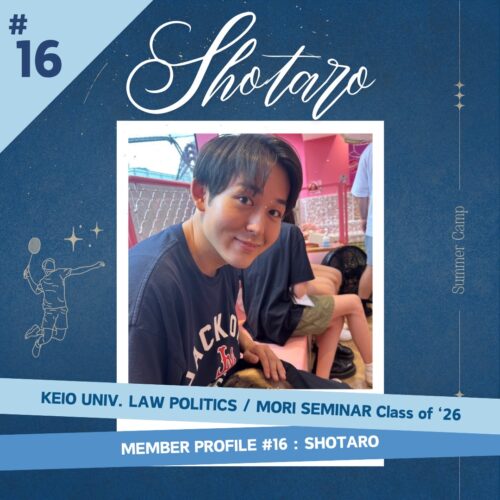
野田尚太郎
3年
合宿係
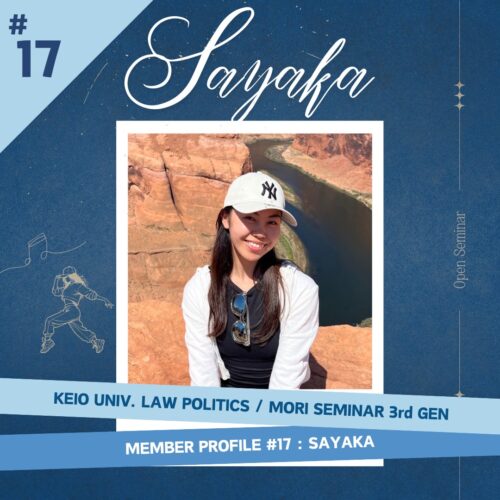
中村咲也香
3年
オープンゼミ係
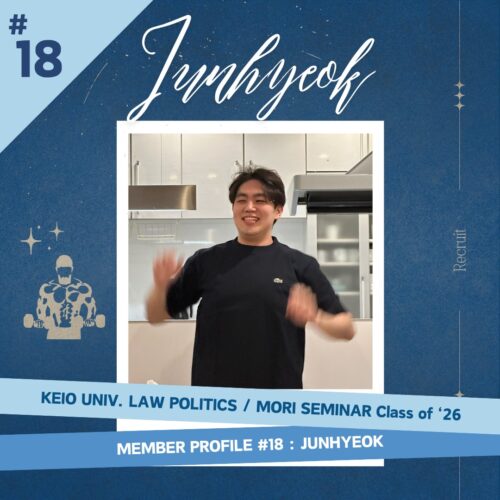
モ・ジュンヒョク
3年
リクルート係

堀井瑞希
3年
オープンゼミ係
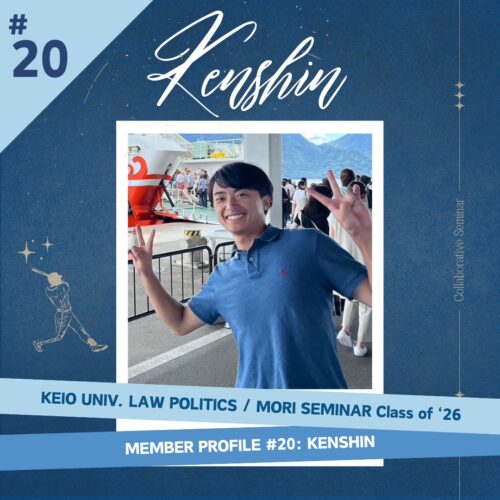
阿部賢伸
3年
合同ゼミ係
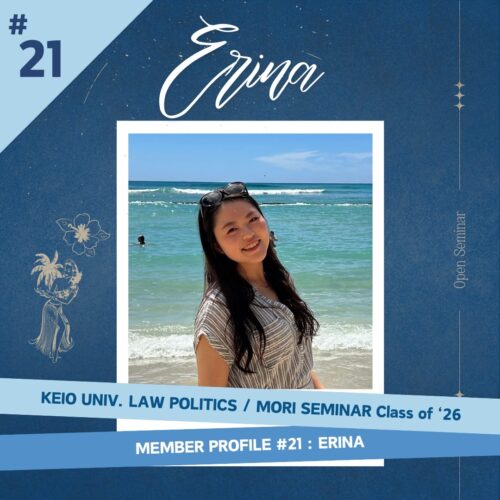
金口英里奈
3年
オープンゼミ係
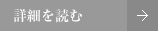
 -夏合宿はじめ、実践的活動について-
森聡研究会では普段のゼミ活動以外にも、実践的な学びを得られる機会がたくさんあります。一例として、2023年度の実践的活動をご紹介します。
4月には、以前外務省で外交官としてご活躍されていた森先生のご紹介で外務省を訪問しました。北米局日米安全保障条約課の前田修司課長より、日本を取り巻く安全保障環境と日米安保体制に関するお話を伺いました。その後、ゼミ生からの数多くの質問に対して大変ご丁寧にお答え頂き、ゼミ生一同多くのことを学ばせて頂きました。
6月には、九州大学の中島ゼミと合同ゼミを行いました。合同ゼミでは、台湾有事を想定した外交シミュレーションを慶應生と九州大生が混同したチームで行い、新鮮な学びを得ることができました。合同ゼミ後は懇親会が開催され、それぞれ親睦を深めました。
8月には神奈川県の葉山で2泊3日のゼミ合宿を行いました。ウクライナを舞台にした外交シミュレーションをはじめ、ディプロマシーゲームという外交をテーマにしたボードゲームをゼミ生一同でプレーしたり、BBQなどを楽しんだりしました。
10月にはアメリカ海軍関係者...
-夏合宿はじめ、実践的活動について-
森聡研究会では普段のゼミ活動以外にも、実践的な学びを得られる機会がたくさんあります。一例として、2023年度の実践的活動をご紹介します。
4月には、以前外務省で外交官としてご活躍されていた森先生のご紹介で外務省を訪問しました。北米局日米安全保障条約課の前田修司課長より、日本を取り巻く安全保障環境と日米安保体制に関するお話を伺いました。その後、ゼミ生からの数多くの質問に対して大変ご丁寧にお答え頂き、ゼミ生一同多くのことを学ばせて頂きました。
6月には、九州大学の中島ゼミと合同ゼミを行いました。合同ゼミでは、台湾有事を想定した外交シミュレーションを慶應生と九州大生が混同したチームで行い、新鮮な学びを得ることができました。合同ゼミ後は懇親会が開催され、それぞれ親睦を深めました。
8月には神奈川県の葉山で2泊3日のゼミ合宿を行いました。ウクライナを舞台にした外交シミュレーションをはじめ、ディプロマシーゲームという外交をテーマにしたボードゲームをゼミ生一同でプレーしたり、BBQなどを楽しんだりしました。
10月にはアメリカ海軍関係者...